【日時】2018年8月25日~26日
【天候】25日晴れのち曇り、15時頃から雷雨で増水 26日ほぼ平水に戻る、晴れのち曇り
【メンバー】こまみの(L)、コバさん
【行程】
25日 宝川温泉先駐車スペース(7:30)-ゲート-ウツボキ沢出会、広河原(11:00)
-大石沢出会付近(12:30)、幕営
26日 幕営地(6:00)-二股(7:30)-大烏帽子山コル(8:50)
-ジャンクションピーク(10:30)-朝日岳分岐(10:45)-大石沢出会(12:10)
-広河原(12:50)-駐車スペース(15:10)
カテゴリー別アーカイブ: 沢登り
会山行 甲武信岳 釜の沢東俣
【日時】9/10(土)~11(日)
【山域】奥秩父 甲武信岳
【行程】
10日:西沢渓谷駐車場8:50発~田部重治文学碑9:25~釜の沢出合13:10~両門の滝14:40~1600m付近幕営
11日:起床4:00~出発6:00~木賊沢出合8:00~ポンプ小屋9:00~甲武信岳9:40~甲武信小屋~まき道~戸渡尾根~近丸新道~西沢渓谷駐車場14:30
【メンバー】なべたけ、こまさん、岳(CL)、ジャイアン、わたゆき、みのさん、ふーちゃん
9月の会山行は、6月に予定していた釜の沢東俣のリベンジとしていってきました。
天候は、土曜曇り、日曜は曇りのち雨の予報であまり期待できない気持ちでいましたが、
運よく土曜日、日曜の午前中は晴れて初夏のようなすがすがしい沢登りとなりました。

林道を歩き、鶏冠山のルートから東沢に入っていきました。沢に入ると沢靴には着替えます。ハーネスはまだ取り付けませんでした。
岩が白くナメ状のものが多く、沢の色も深いところはエメナルドグリーンに輝き、癒されます。


わたれないところは、高巻きしながら進んでいきますが、なかなか釜の沢の入り口にたどり着きません。
出発してから4時間ちょっとで釜の沢出合に到着。13時過ぎ。夏合宿の越後でのビバーク体験からこの時間から登り始めることへの恐怖心がよみがえりましたが、16時には到着できそうとのことで、安心してハーネスを装着しました。
釜の沢にはいってす少し歩くと、この沢のメインといってもいいか分かりませんが千畳のナメ。心地よい。

ナメを伸びのぼりきると両門の滝30メートル。両サイドから水が流れ落ちてきます。

両門の滝の右側のマヨイ沢の方に高巻きをし、今日のビバーク地へ。高巻きをするとき、こまさん、なべたけさんとわたゆきさんが蜂にさされ、特に最後にきたなべたけさんは集中攻撃にあいました。
ビバーク地には、3パーティがすでにテントを張っていたので、50メートルくらい進んだ平坦な場所に、幕営。今宵の食事担当はこばさんで、牛ステーキ肉が半額だったので、串焼きとトマトベーコン、たまねぎ丸ごとホイル包みなど焚き火を使った贅沢ごはん。締めはトマトリゾット。次の食事担当にプレッシャーが沸いてきそうです。笑

翌日、甲武信ヶ岳までの残りの距離、下山時間を考えて、4時起床、6時出発!樹林帯の踏み跡を進んでいきます。
ミズシ沢と木賊沢の出合のしたに10メートルの滝があり、高度があったため、ロープを使って登りました。他のパーティはロープを使ったり、使わなかったりしていましたが、登ってみると流れる沢の中に足場があり、登れるルートがあることにきがつきました。
その後沢をのぼってポンプ小屋に到着。お疲れ沢~。
ここで沢道具をザックにしまって甲武信ヶ岳へ。こまさん、わたゆきさん、なべたけさんは体調不良のため、甲武信小屋迄のぼり下山。

その後、それぞれのペースで下山。お疲れさまでした。

個人的には今年最後の沢の締めくくりとして取り組みましたが、まだ沢靴と自分の重心移動がうまくできず急斜面のナメをスムーズに歩くことができず、滑りそうで怖かったです。来年がんばります!
皆さん、楽しい山でのお時間ありがとうございました。
夏合宿A隊 只見川水系 中ノ岐川二岐川本流(平ヶ岳先ノ沢)
期間:2016年8月11~13日
メンバー:L:reiko、SL:sobe、morimaro、koba、fumi、komamino
8月11日(木) 快晴
道の駅ゆのたに駐車場(仮眠)=雨池橋(7:50)~二岐川林道(8:20)~曲沢橋(8:50~9:00)~檜枝岐小屋跡(11:35)~壊れた堰堤(11:40~12:00)~巻嵓沢出合(13:25)~タンスノ沢出合(16:15)~100m6段大滝上(19:00)
~ビバーク地(19:30)
前夜、22時橋本駅に集合。関東は午後からの豪雨の影響で小田急線、京王線に遅れがあったが、集合する頃には雨も上がっており、ほぼ全員時間通りに集合して出発することができた。morimaroさんとは翌朝道の駅で集合することになっていたが、私もmorimaroさんも体調が思わしくなく、現地で計画変更もあり得る状況での出発だった。
8月11日は今年から祝日「山の日」で、行きでの渋滞も予測したが、順調に道の駅に到着し、テントを張って仮眠。
6時30分、morimaroさんと合流し、雨池橋に移動。昨年の夏合宿に続いての雨池橋だが、今年は2台駐車してあるのみで、ゆったり駐車することができた。
計画は二岐川本流を遡行し、途中で尾根を乗越し、恋ノ岐沢を下降することになっており、車1台を恋ノ岐沢出合に駐車しておく予定であったが、morimaro、reikoの体調で中ノ岐林道に下る可能性が高いため、2台とも雨池橋に駐車して出発した。20分ほどでナメの美しい二岐川本流の出合に着く。更に10分ほど歩き二岐川林道入口に到着。注意しないと林道入口の橋は草に覆われて見落としやすい。林道とは言え、道はかなり荒れている。30分ほど歩いて、支沢にかかる橋に到着。道は所々ぬかるんでいるため、ここでウェディングシューズに履き替える。しばらく進むと、komaminoさんが遅れ、見ると靴の右足のソールが踵から土踏まずまで剥がれていた。小屋の沢手前でテーピング用テープで応急処置をする。まだ沢の遡行も始まっていない状況で、どうしたものかと思案しながら進む。檜枝岐小屋と思われるつぶれた小屋があり、車が埋もれている。かつて車でこの林道を入れたとは信じがたい。やがて暁の会報19号に中村さんが書いた遡行記録にある、幕営適地の壊れた堰堤に出た。確かに焚き火もでき、快適な幕場だ。
komaminoさんの靴は、補修したテープは切れてしまい、全員ここまでか、と途方に暮れていると、kobaさんが結束バンドを持っており、フェルトの踵部分2ヶ所にナイフで穴を開け、結束バンドでリングを作り、わらじの要領で靴に結びつけ、何とか先に進めそうな状況になった。ただこの先標高1400m付近まではゴルジュ帯で、幕営適地はない。morimaro、reikoの体調も考え、ここでの幕営を検討したが、まだ時間的に早いとの意見もあり、先に進むことにする。


ここから遡行を開始し、やがてジョウ沢出合に着く。沢はほぼ1:1だが、ジョウ沢のほうが沢床が高い。合宿中本流で魚影を見ることはなかったが、誤ってジョウ沢に入ったkobaさんの話では、岩魚がいっぱいいたとのことだった。
やがて5m逆く字滝と思われる滝に出会う。左岸側から巻くが、降り口がなく、結局巻嵓沢出合の滝上に降りる。巻きにかなりの時間を費やした。その後も5m程度の磨かれた滝が次々と続き、微妙なへつりやツッパリで越えていく。

時にはドボンする人もいたが、釜に落ちてみんなの笑いを誘った。雪渓がまったくないためか、思いのほか時間がかかり、100m6段大滝が始まるタンスノ沢出合を通過したのは16時を過ぎていた。それでも大滝に関する多くの記録から難易度はそれほど高いものではなく、1時間程度で登りきり、ゴルジュを抜けられると考えていた。しかし実際には大滝を登りきるのに5ピッチかかり、沢床に降りた頃には夕闇が迫っていた。今回の山行中、まったく雪渓を見ることはなかったが、多くの記録では、この大滝には雪渓が詰まっており、そのため比較的短時間で抜けられたのではないかと考える。
とにかく明るいうちに少しでも先に進み、幕営地を探したかったが、19時を過ぎあたりは暗くなり、目の前に深い淵の滝がかかり、これ以上の遡行は危険と判断し、思案する。ゴルジュの中ではあるが、かろうじて6人が夜を過ごせそうな岩があり、幸いにも夕立もなく夜間の増水はないと予測されたため、その場でのビバークを決めた。計画書通りの夕食を作れる状況ではなかったので、まずはお湯を沸かしてみんなで暖かいカフェオレを飲んだ。いつもは甘い飲み物はそれほど人気がないが、この時ほどおいしいと感じたことはない。みんな少し落ち着きを取り戻し、副食のマッシュポテトを作ったり、各自つまみや焼酎、ウイスキーのお湯割りを少量飲み、眠れないかもしれない夜に備えた。
各自あるものをすべて身に付け、また増水、落石に備えてハーネス、ヘルメットも身に付けて、3人ずつに分かれて、ツェルトやタープを被って体を横たえた。ゴルジュの中から見える狭い空は満天の星で、時々流れ星を見ながら寒さに耐えた。
8月12日(金) 晴れ
ビバーク地(6:05)~1400m幕営適地(6:50)~1452m二又(8:05)~1539m二又(8:50)~1650m恋ノ岐沢乗越への支沢(10:21)~支尾根~姫ノ池(14:40-15:24)~平ガ岳沢横断点幕営(17:50)
寒さに耐えられず、明るくなると早々に起きだした。明るくなって見ると目の前の淵はかなり深く、昨夜突入しなくて本当に良かった。温かい飲み物で冷えた体を温め、朝食のそうめんも温かいスープに変更し、身支度を整える。目の前の淵は左から微妙なトラバースで突破。40分ほどで左岸側に快適な幕営地を発見。1時間早く出発していればたどり着けたのかと思うと残念だが仕方がない。ゴルジュを抜け、日も差して徐々に体も温まり、水と戯れながら、へつりやつっぱりで次々と現れる滝やナメを越えていく。やがて1539mの二俣(1:1)を通過。間もなく計画していた恋ノ岐沢下降のための乗越しに突き上げる沢が左に滝を掛けて出合う。このあたりから沢はもう源頭の様相で流れも細くなる。忠実に本流を詰めて行くが、次々と5~6mの立った滝が続き、安全のためザイルを数回使用する。細い流れながら、最後の一手がない滝に、今回の山行中唯一の残置ハーケン、シュリンゲがあり、助けられた。できるだけ藪漕ぎせずに姫ノ池に出るため、最後の二俣で左にルートを取りたかったがザレた滝がどうしても越えられず、やむなく右にルートを取る。最後は草付きの藪を漕いで青木山に続く稜線に出たが、ここから笹とはい松、石楠花との格闘が始まる。背丈以上の藪で見通しが利かないため、コンパスとにらめっこで進む。悪戦苦闘の末、姫ノ池の湿地に出て視界が開けた。

沢の装備を外していると、恋ノ岐を詰めてきた4~5人のパーティが現れ、互いの情報を交換しあった。彼らは姫の池に1泊するようだが、我々は泊りの水もないため、平ヶ岳山頂はあきらめ、がんばってプリンスロードを下り、中ノ岐林道まで下ることとした。急な下りは2日間の疲れた体にはかなり応える。もう限界と思う頃、登山道は平ヶ岳沢を横切る橋に出会う。今日の泊りはここしかないと、みんなザックを下ろし、濡れた物を広げ、焚き火や夕食の準備に取り掛かる。
みんなで焚き火を囲み、長かった2日間に思いをはせる。予想以上に厳しい山行となったが、今回の経験がこれからの山行に生かされることを祈るのみ。
8月13日(土) 晴れ
幕営(7:50)~中岐林道(6:45)~二岐川本流出合(10:40)~雨池橋(11:00)
本日は林道を歩くだけのため、起床は6時30分としたが、6時前からマイクロバスで送ってもらったと思われる登山者がテントの横を次々と通り過ぎて行くため、6時にはみんな起きだし、朝食の準備を始める。
焚き火の後始末をして出発。5分ほどで林道終点、トイレも水場もある。マイクロバスが1台止まっているが、運転手の姿は見えない。
今日も快晴で、暑い林道歩きになりそうだ。30分ほど歩いた頃、なにを思ったのか千々和さん、kobaさんが走り始めて、あっという間に姿が見えなくなった。昨日の藪漕ぎで2人は後のほうで苦戦していたはずだが、あの時体力を温存していたものと思われる。
林道を横切る主な沢には沢の名前が書かれた札が立てられており、現在地の確認に役立った。灰ノ又山に突き上げるハコジョウ沢、二岐川手前の滝沢など、出合に素敵な滝を掛け、心引かれる。10時30分、一昨日出発した二岐林道入口を通過。再び雨池橋に戻り、3日間のA隊夏合宿は終わった。
本来なら今回のメンバーで事前に沢でのトレーニングを重ねるべきだったが、私自身リーダーでありながら、なかなか会の山行に参加できず、トレーニング不足は否めない。またmorimaroさんも私も直前に体調を崩し、万全の体調ではなかったこと、komaminoさんの沢靴が入渓前に壊れたこと、私を除いて沢のビバークはみんな初めてであったこと等など、反省すべき点は山ほどあるが、弱音を吐くことなく、どんなときにも笑いの絶えなかった今回のメンバーに感謝。
記 reiko
夏合宿B隊:越後 黒又沢五竜沢

 山域 黒又沢五竜沢
山域 黒又沢五竜沢
日 2016年8月13日(土)〜15日(月)
メンバー nave take(CL)、gaku
8月13日(土)
天気 晴れ時々曇り
行程 十字峡登山センター(6:15)〜五竜沢出合(8:00)〜両門の滝(14:00)〜幕営地(17:00)
前夜21:00に相模原発。関越経由で六日町ICから十字峡へ。
十字峡には1:00頃到着。
この日はなんとか流星群がピークらしい。眠る前わずかな時間、満天の星空を見上げると流れ星がふたつ流れた。
5:00にはほとんど明るくなるが、6:00すぎに遅めの出発。中ノ岳登山口から3m登ると、黒又沢への分岐が左にあり、ダムの脇を黒又沢へつたっていく。
早朝だが、黒又沢の水は冷たくはない。今年は積雪が少なく、雪渓はかなり少ないと言われている。なんとなくだが水温からも雪渓の少なさを感じた。
荒涼としたというか原始的な印象の広いゴルジュを黙々と進む。昨年遡行した日向沢、明日の下降ルートとして予定している御神楽沢を通過していく。
狭くなったゴルジュ帯の淵をへつりながら、徐々に緊張感が増していく。五竜沢はガイドブックによると中級の沢とあるが、果たして何を基準にしたものなのか。
navetakeは越後の沢は、一昨年の高倉沢と昨年の日向沢を遡行している。丹沢や奥多摩などの沢とは別物のような印象だった。gakuさんは昨年、灰ノ又と恋ノ又を遡行しているが、経験の少ない私たちにとって今回はどんな山行になるのか。
鉱山の名残の鉄橋と、左岸側壁からダムの放流のような大量の水が注ぐ箇所を横目に、進んでいく。右岸から曲沢、続いて五竜沢が合流してその先は、深い淵となっていて行く手を阻んでいるようだった。
五竜沢出合まで2時間。1時間30分くらいで来れたらと考えていたが、そこから甘い見積もりだった。
遡行図によると、出合から3m、5m、2m、6m・・・と連瀑が続く。「登攀的な沢」というガイドブックの通り、滝の登攀力が問われると思っていたが・・・。
7月に、丹沢の中では困難度が高いと言われている同角沢を主要な滝を全て直登して遡行していたこともあり、ある程度自信を持って臨んだ部分もあったが、それはあまり通用しなかった。
一見登れそうな滝も、取り付いてみると手掛かり足掛かりが乏しかったり、外傾していたり・・・。また、いつもは当たり前に存在しているハーケンやお助けスリングなどの残置物が一切見当たらない。
ここは無理をしないでと、高巻きに移ると・・・今度はマツコ、いや私たちの知らない高巻きの世界。高巻きという名の登攀。ホールドは、信頼度の高い潅木と、根強そうな草付き。スタンスは、不安定な泥壁。
もともと高巻きのセンスがない(navetake)うえに、落ち口へのトラバースも側壁の傾斜のプレッシャーから、どんどん上部へ登っていく。藪の中を15m〜30mほどの懸垂で沢へ戻るということを何度か繰り返した。
踏み跡らしきものは、まったくと言っていいほど見当たらない・・・。


唯一、両門の滝25mをnavetakeが(いつも以上にビビりながら)リードしたことで、少しは溜飲が下がったか。ここも残置は皆無。ハーケン4本とナッツ1でランニングをすべて作って登る。滝上では、ハーケンとナッツでビレイ点を構築した。
(たしか)両門の滝の次の滝を高巻いて降り立ったゴーロの河原で本日の行動終了。
早い段階で受傷していたgakuさんの踵は、表面が内出血して少し腫れていた。滝に取り付いたが登れず、やや無造作に釜に降りてしまっため沢床に当たって受傷してしまった。痛みはそれほど強くはないようだ。
天気は良く、河原には乾いた薪が豊富で、快適な幕営地だった。軽量化のため、共同のテントは持参しておらず、各自ツェルトビバークをする。

8月14日(日)
天気:曇り時々晴れ
行程:ビバーク地(6:00)〜稜線登山道(14:00)〜五竜王大神の池(15:15)
この日もすっかり明るくなってから遅めの出発。天気はまずまず良さそうだ。
と、ビバーク地から5分で7mの直瀑前へ。落ち口の両端は数メートル切り立っていて、威圧感がある。
朝イチから容赦などない。左岸からお勤め開始である。30mほどルンゼ状を登り、尾根に出て反対側の沢床へ懸垂で下降した。
昨日1日を経て、私たちは多少なりとも諦観してきていた。これは修行なのだ。
時間が順調に過ぎていくなか、ジリジリと進んでいくしかない。
最後の大滝になる25m滝は、ガイドブックには左壁をハーケン3枚で登ったとあり、navetakeがリードトライするが、細かいスタンスとホールドしか見つけられない。左端の凹角を7〜8mほど登ってみたが、上のややせり出した岩の上はスラブで手掛かりがなさそう・・・。右へトラバースするには、ロープの流れが悪い。結局、ハーケン1枚残置して下降、左岸を巻いた。
昨日もそうだったが、取り付いて結局登れないと、その分時間のロスになる。登れるかどうかの見極め、時間配分もなかなか難しいところなのだろう。
それにしても、やはり雪渓は全く見られない。標高1000m付近で雪塊が見られたが、1週間もすると溶けてなくなってしまうかもしれない。
少しずつ水量が減り、ゴーロ帯に移っていく。稜線はまだまだ遠い。巨岩の間を縫うように攀じのぼる。水線は、消えては現れ、現れては消える。結構終盤まで残っていた。


五竜岳へ伸びるゴーロ帯から、阿寺山への稜線へ向かう登山道のような支沢に入る。草付きの藪をかき分けて稜線を目指す。アブがうるさい。gakuさんが、阿寺山方面へ絶妙にライン取りをしながら、一般登山道に出ることができた。
すでに14:00。今日中に御神楽沢を下降するのは難しいだろうと話し合っていた。
稜線に出て携帯のアンテナが立ったので、行動予定の変更をメールする。ついでに、明日の天気予報をチェックすると、午後から雨の予報。
15:15、御神楽沢への下降点である、五竜王大神の池に到着。
明日の天気を考え、できる限り御神楽沢を下降しておいたらとも考えたが、地形図上では平坦な箇所はなく、無理をせず、池のほとりでビバークすることにした。
予定では1泊2日の行程で、できる限りの軽量化の考えから、十字峡を出発する際に、予備食はアルファ米1食分としたため、夕食はコンソメスープに高野豆腐を入れたもので済ませる。アルファ米は明朝に残しておいた。
アプローチシューズも、御神楽沢の下降ならいらないだろうと十字峡に置いてきたが、長時間の沢靴の歩行に疲労度が増していた。
軽量化とのバランスを考えていかなければならないが、これも経験だろう。
アルコールもなく、宵の口からそれぞれ、シェラフカバーとツェルトと山の闇にくるまって疲れを癒す。明日は、3:45起床予定とした。雨が降り出す前に下山したい。
夜半、小雨が降り出す。天気の悪化が早まったのか。夜明けまで断続的に降っていた。
navetakeは空腹と、降雨でツェルトを頭まですっぽりとかぶる息苦しさから、熟睡ができない。
gakuさんは、いびきをかいて気にする様子はない。
8月15日(月)
天気:小雨のち晴れのち雨
行程:五竜王大神の池(6:00)〜阿寺山〜山口(9:30)
本日8月15日、終戦記念日。
明るくなって雨は止んでいるが、空は所々雨雲がかかっていてはっきりしない。
夜の雨で、沢の下降は難易度が増していると考え、阿寺山経由で下山することを決めた。御神楽沢の下降は核心の一つと考えていたが、正直ほっとしていた。
下山し始めると、次第に雲が薄くなっていく。沢筋に入ると日が出てきていた。天気の変化が前倒しになったのだろうか。
残念な気持ちはあまりなかった。下部に大滝を持つ傾斜の強い御神楽沢を下降するには、私たちには不安要素が多いと感じていた。
広堀川の途中の露天風呂のような釜に浸かって汗を流し、山口へ下山した。
午後からは、また雨が降り始めた。
あとがき
2日目の朝、1時間早く行動を開始していたら、滝を登れるか登れないかの判断をもっと適切に行えていたら、もっと御神楽沢について下調べが出来ていたら、予定通り御神楽沢を2日目に下降できたかもしれなかった。
なかなかチャンスは限られているので、そんな積み重ねを少しずつでも大事にしていけるようにしたい。
小川谷廊下
南アルプス 鳳凰三山 シレイ沢
【日程】2016年7月16日(土)~17日(日)
場所:南アルプス・シレイ沢
【工程】シレイ沢橋~シレイ沢~二俣~奥ノ二俣~観音岳~薬師岳~夜叉神峠
【メンバー】morimaroさん(L)、Kobさん、Zakky-さん、みのさん、fumiko(食担)
【天気】16日くもり時々晴れ、17日晴れのち雨
morimaroさんから会のメンバに鳳凰三山のシレイ沢へのお誘いがきたため、私は沢登り経験4回でしたが、南アルプスでの沢登りにいくチャンスは二度とないかもっと思い、参加させていただきました。
当初は日曜から月曜の1泊2日の予定でしたが土曜日の方が天気がよさそうとのことで、金曜夜橋本発となりました。
夜叉神峠の駐車場に車をとめて、乗りあいタクシーでシライ沢橋で下車し、さあ、沢の準備。日帰りの沢登りしか経験がないうえに、荷物が重たく、不安なはじまりでした。
スタートで、橋から沢へ降りられそうな場所が見当たらなかったため、いきなり懸垂下降~。
倒木をかき分けて上っていきました。奥多摩や丹沢とは違った高さのある滝が多く、高巻きしながら進んでいきました。






翌朝4時起床し、朝食をたべて、6時に出発。


今回の沢は、高巻きが多く、しっかりつかむところが少ない細いトラバースを進まなければならない場面が多かったです。4番目で歩いていたので、どんどん地面が崩壊して滑落しかけました。
常に集中して、気を抜けない(常に気を抜いてはいけないのですが・・・)ところが今まで経験した沢とは違うところでした。最後の藪漕ぎも急斜面が続き、最後は、砂のザレ場を登るという非常に体力が必要とされ、久しぶりに筋肉痛になりました。それでもみんなで力を合わせ無事に登りきり、下山できたことは何よりです。
みんなどうもありがとうございます。
その後、芦安の温泉にはいり、台湾料理屋で炭水化物をとり、Morimaroさんは、名古屋方面へ、それ以外の4人で橋本に帰るわけですが、次の日も4人でジムにトレーニングしにいくという、何かに取り付かれたように登ることにはまった3連休でした。
詳しい沢情報は、こちらのMorimaroブログで確認!↓
http://morimaro.at.webry.info/201607/article_3.html
7月会山行 奥多摩 真名井沢
2016年7月10日(日)
奥多摩 真名井沢
メンバー koma、gaku、fumi、yamaken、watayuki、
navetake(L)
当初の計画では、土日で釜の沢東俣に入る予定だったが、
週末に前線の通過が重なり、大雨の予報。
sobeさんからリーダーを託されたnavetakeだったが、早々に諦めの境地に。
釜の沢は延期にさせてもらい、土曜日の夕方に入渓点まで入り幕営、日曜日に真名井沢の遡行を楽しんだ。
結果、前線はやや南よりの進路だったので、奥秩父にはそれほど雨雲がかからなかったようであり、釜の沢の遡行も可能性があったようだったが、
美渓は、コンデションが良い時に入りたいということで、
皆様、どうかお許し下さい。
また、滝の登攀ではアクシデントがあり、幸い大事には至らず怪我も少しで済んだが、あってはならないミスであり、大切な教訓になった。
参加メンバー全員にとって、大きな学びにしなければならない。
山は教室、登山は教科書。
必要なことは、山が教えてくれる。
もっともっと真剣に、山と向き合おう。
玄倉川水系同角沢
7/2(土)同角沢を遡行しました。
メンバーは、morimaro、navetake、gaku(L)の3名。
僕は上級クラスの沢は初体験。
同角沢には三重の滝(2段20m)、不動の滝(30m)、無名の滝(20m)、遺言棚(3段45m)とロープを出した方が良い登攀要素の強い大きな滝が4つあります。



僕自身がこれら四つの滝を前にしてどうなるのか。
ビビって登れないのか、興奮して突っ込んでしまうのか、意外と冷静に登れてしまうものなのか。
さてさて、どうなるもんですかねぇ。
そんな感じのテンションで、計画を立てておりました。
結果、全ての滝を意外と冷静にリードできてしまいました。


3月から毎週一回は定期的にクライミングジムに通い初めたこと、
命を預けるザイルパートナーがmorimaroさん、navetakeさんと経験豊富な心強いお二人であること、
梅雨時期の割には水量が少なかったこと、
前日も雨ではなく、それほど脆い砂壁の状態が悪くなかったこと、
毎週、山に通い続けていることで自分の集中力や判断力が途切れることがない体力がついていること、
GWに丹沢横断カモシカ山行を経験していたりハードな登山も繰り返していること、
無名の滝の前に、不動の滝で水流の中のトラバースをしたこと、
無名の滝のクラック上のハーケン二本が脆いことにあまり気づいてなかったこと、
遺言棚の最上部の灌木がある程度太かったこと、
全ての条件が重なっていたからこそ、たまたま、冷静に登れたのだと思います。
少し水量が多かったり、大雨の翌日だったり、十分なトレーニングができていなかったら、登れなかったことでしょう。
会心の登攀を経験させてくれた全ての出会いに感謝であります。
無名の滝登攀中、滝を浴びながらハーケンを打っている時、ふと、初登者の方の熱い思いが乗り移ったような感覚になりました。

滝上部の脆い壁を数mランナウトしている時、冷静と情熱と興奮と幸福感と全てが入り混じった濃密な時間を過ごせました。
アルパインの入口に立ち、奥から漂う甘美な誘惑に抗うのは僕には難しいように思えます。
ますますアルパインの世界に没入していきそうな自分の身を守るためにも、継続的なトレーニング、技術の研鑽、精神の鍛錬を怠らないようにしなければいけませんね。
今回の反省点としては、遺言棚登攀後、地形図を確認しこれから進むルートの確認を怠たったこと。
間違った尾根に上がってしまい、余計な時間をとり、無駄なエネルギーを消費しました。
偶然、同じ間違いをした先行パーティの一助になれたことは、不幸中の幸いでした。
もしかするとそういう流れだったのかもしれません。

下山後、ユーシンロッジ前の広場で、ツェルトも張らずシュラフカバーだけで眠ったのも、幸せな時間でした。
翌日は、ヤシロ沢遡行の予定だったのですが、水量が極端に少ないこと、気温が高すぎることから遡行意欲は全くわきませんでした。
ヤシロ沢出合いから檜洞沢の途中までを、気の向くままお散歩したり、昼寝したりしながら歩きました。
夏の沢を満喫した二日間となりました。


■1日目の同角沢
■二日目のお散歩したルート
■森麻呂さんのBlogはこちら
生きて戻れて良かった! 西丹沢・玄倉川・同角沢遡行+檜洞沢散策
新茅ノ沢:6月会山行
【日程】6/11(土)
【メンバー】yamaken,komamino,gaku(CL)
【ルート】新茅橋~新茅ノ沢~烏尾山~仲尾根~モミソ沢懸垂岩
6月会山行では沢隊が3パーティーもできました。
参加する層が厚くなってきました。嬉しいことです。
リーダー層が増えリーダーの実力もついてきたら、さらに会全体の活動も充実してくることでしょうね。
頑張って自己鍛錬に励みましょう!
新茅ノ沢は滝の登攀が前半にコンスタントに続く楽しい沢でした。
大滝の直登を全員できたのが、とても嬉しかったです。


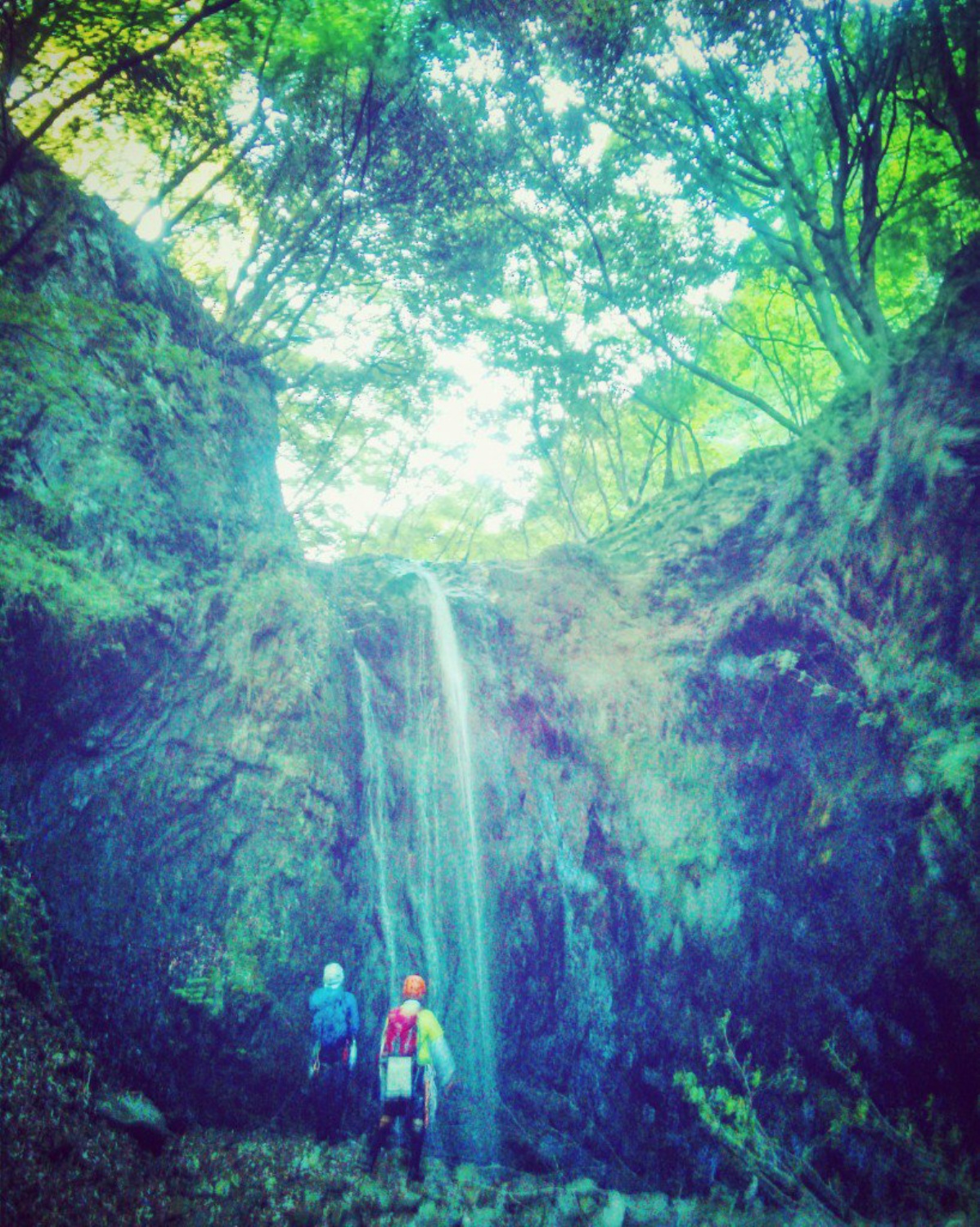



下山後はモミソ沢の懸垂岩に行って、カラビナ&半マストでの懸垂下降。
支点の構築方法と注意点。フォローのビレイ。登り返し。懸垂下降中の結び目の通過等を練習しました。
日が傾いてきたので、戸沢のキャンプ場へ向かい、B・B・Q!

元会員Tさんの山話をたくさん聞けました。Tさんの山への熱い情熱を少しおすそ分け頂いたような気がしました。

水無川本谷:6月会山行
【日程】6/11(土)
【行程】戸沢出合~金冷シ沢出合~塔の岳
【メンバー】morimaroさん(L)、こまさん、fumi
【天気】快晴!
救助トレーニングの前に3つのグループにわけて、沢登り。
Gaku,Yamaken,Komatin さんは新茅ノ沢〜烏尾山へ
なべたけ、なべゆきさんは、源次郎沢へ
私自身の沢登りは、3回目、今年初で少しドキドキしながら3人で、真ん中の位置で沢を登って行きました。
新緑の季節、梅雨晴れで、緑の香りがきもちよかったです。
3回目の沢にして、快晴あり、沢の水が気持ちよい、体力や岩登りの技術が少しついたこともあり、沢登りの楽しさを知った一日でした。
morimaroさん、komaさん、暖かく見守って下さりありがとうございました。また、沢登りしたいです。
F1、左からロープなしで登ります。





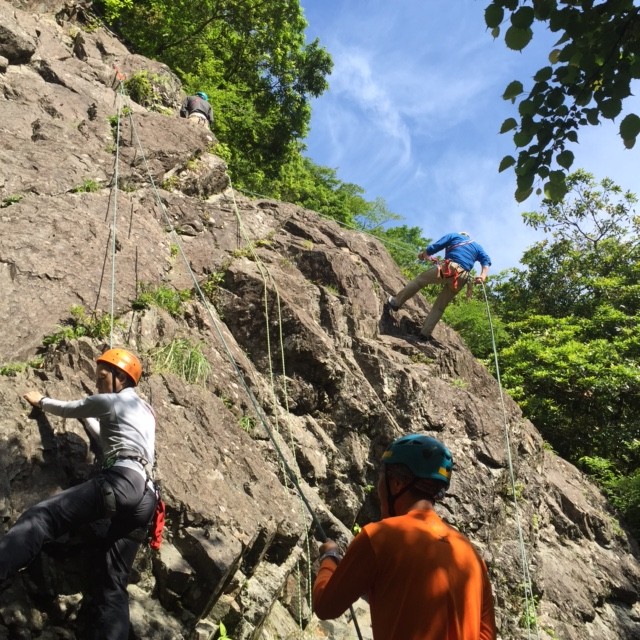
morimaroブログはこちら↓





















