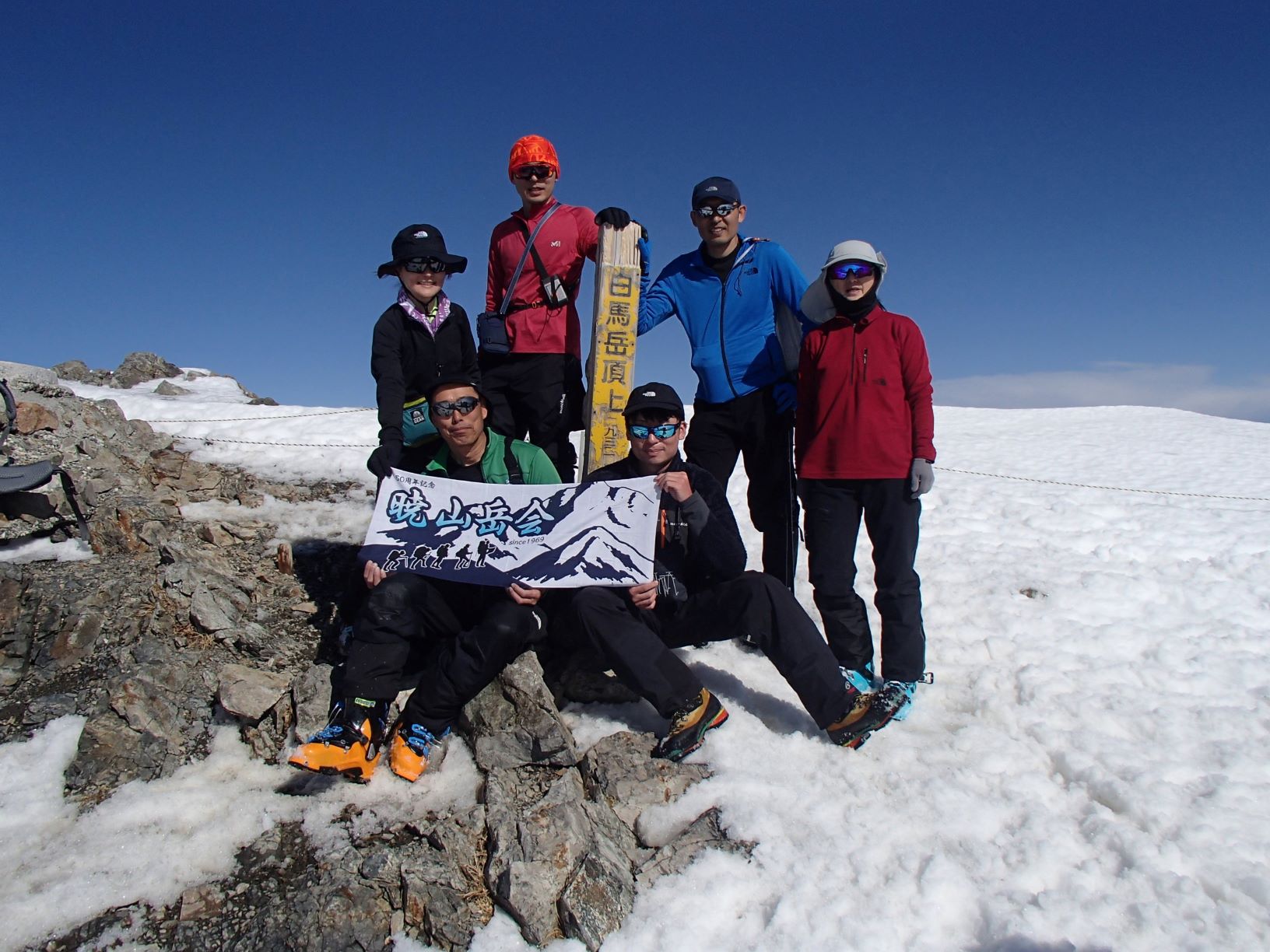期 日:2022年4月29日~30日
参加者:Lヨッシー、ヒー
4月29日(金)曇りのち雨
新穂高温泉駐車場(10:40)-笠新道手前(12:55)幕営
道路渋滞のため予定より遅れて出発。すぐにA隊と別れ左俣林道に入る。林道に雪は殆ど無く、中崎橋の手前でスキーを履くがすぐに雪が途切れる。12時くらいから雨が降り始める。笠新道のすぐ手前の広場にテントを設営する。水は左俣谷から得られた。やや強い雨が夜半まで降り続き、朝方には霧雨になった。
4月30日(土)霧雨のち晴れ
幕営地(5:20)-ワサビ平小屋(5:35)-小池新道登山口(6:15)-秩父沢出合(7:20)-旧大ノマ乗越分岐(8:35)-2400m地点(10:25)-小池新道登山口(11:40)-幕営地(12:30)-新穂高温泉駐車場(14:35)
3時20分頃、奇声を発して通り過ぎる登山者がいた。笠新道に向かったらしい。外は霧雨で視界はない。熊鈴代わりの奇声なのか?テントを置いて出発。ワサビ平小屋でスキーを着ける。小池新道登山口までの間も雪が切れている所があったが、小池新道からは雪が途切れることはなかった。無駄な登りを避けるため、細いスノーブリッジを渡ったり少し藪っぽい夏道沿いを行ったり・・。秩父沢からはべったりと雪が付いており歩きやすい所を登る。

天気も回復し、目指す弓折岳が見えてきた。大ノマ乗越を目指すと段々傾斜が強くなってきた。乗越が見えてきた辺りで30センチほどの落石がヒーさんめがけて落ちていく。10mくらい手前で方向が変わり事なきを得た。途中A隊と連絡が取れ、早めに下山するとのこと。下りにかかる時間や体調のことを考慮して2400mを最高到達点とする。

乗鞍岳から槍穂高岳の眺めを暫し堪能してから滑降開始。滑りやすい斜面だ。小池新道登山口まであっと言う間だった。幕営地に戻り一時間かけてテント撤収。ここからまた苦行が始まる。ゲートの先までオヨシが迎えに来てくれた。靴を持って貰う。助かる。ゲートまで車を上げて貰いさらに助かる。
(記 ヨッシー)